オノ・ヨーコはなぜ、今もなお世界から注目を集めるのか。オノ・ヨーコスタジオのディレクターで、現在、小山登美夫ギャラリーで開催中の個展『A statue was here 一つの像がここにあった』のキュレーターも務めたコナー・モナハンに話を訊いた。
地球が回る音を聴きなさい。
第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展──青木淳がキュレーターの日本館などをレポート
想像しなさい。
千の太陽が
いっぺんに空にあるところを。
これはオノ・ヨーコの著書「グレープフルーツ・ジュース」の一節だ。こうした人々の自己観察を促し、世界の見方を変えるような「インストラクション(指示書)」の作品を含め、絵画、彫刻、パフォーマンス、映画、音楽、また鑑賞者の参加型作品多様な表現で、社会に大きな影響を与えてきたオノヨーコ。
現代美術家として70年以上にわたるキャリアを持つ彼女だが、昨年、開催された英国のテート・モダンでの大規模な個展を筆頭に、現在もベルリンの複数の美術館でソロショーが開かれるなど、今、改めて、その作品が世界で注目を集めている。この6月には、小山登美夫ギャラリーの六本木・天王洲の2つのスペースで個展「A statue was here 一つの像がここにあった」も始まった。
なぜ、今なお、彼女の作品に人々は惹かれるのか。「A statue was here」展のキューレーターで、オノ・ヨーコスタジオのディレクターでもあるコナー・モナハンに、本展の見どころと合わせて話を訊いた。
──昨年、テート・モダンで開かれたオノさんの個展が大きな反響を呼びました。現在もベルリンの3カ所以上の美術館でエキシビションが同時開催されています。今もなお、オノさんの作品が人々の関心を惹きつける理由はどこにあると思いますか。
ひとつは、ヨーコの作品が、単なる美的なものを表現した作品ではなく、鑑賞者に想像を促したり、また物理的に参加させたりするものであることが挙げられると思います。美術館での人々の関心を見ていると、近年、来場者はアートに参加することや、関わることを切望していることころがあり、同時に、美術館自体も今、人と関わりを持つ場所として、その役割が求められています。だから近年、美術館も以前よりも増して、ヨーコの作品を展示し、紹介することに期待を寄せているように感じます。
また、世の中の認識や見方も大きく変わりました。かつて、ヨーコが積極的に創作活動を行なっていた60年代や70年代は、女性蔑視や人種差別がある時代で、多くの人は、女性で日本人であるヨーコを、アーティストとして見なすことにためらっていたところもあったと思います。
「ずっと正しく評価されてこなかった」しかし、今の若い世代の多くは違います。当時ヨーコがどのように扱われていたかを客観的に見ながら、その逆境の中でヨーコがどれほど強く自分自身を主張し、自分の声、芸術性、信念を曲げなかったかを知っています。そうしたヨーコの信念を貫く姿勢も、今、新しい世代の目には、非常に力強いものとして見えるのだとも思います。そういう意味で、ヨーコの作品は、「昔から長く評価されてきた」わけではなく「ずっと正しく評価されてこなかった」ところもあるでしょう。むしろ、その評価はまだ始まったばかりだとも言えます。
──コナーさんは、オノ・ヨーコスタジオでディレクターを務めています。ご自身では、オノさんの作品のどのようなところに惹かれますか?
そもそも、私がアートに関心を持ったきっかけがヨーコの作品でした。
最初にヨーコの作品を見たのは、17歳のとき。友人に誘われ、地元ミネアポリスの「ウォーカー・アート・センター」で開催されたヨーコの展覧会に行きました。その友人が、ヨーコのファンで、自分のヨーコのレコードにサインが欲しいと、ヨーコに会えるオープニングに行ったのです。実際にその友人は、ヨーコに会うことができ、サインも貰えたのですが、そこで見たヨーコの作品は、私にとって自分自身を解放してくれるものでした。アートというものが、世の中のさまざまな考えに対処する方法であること、私たちの思考を前進させ、人々の考え方や認識を変えることができるものだと、ヨーコの作品を通して知ったからです。
「存在するもの」と「存在しないもの」のバランスそして、私は、大学で美術を学び、美術の道に進むことを決め、ヨーコのスタジオの門を叩きました。だから円を描くように、ヨーコのところに戻ってきた感じです。
ヨーコの作品に惹かれるのは、その後17年以上一緒に仕事をしてきた今でも、アートの見方、ひいては世界に対する見方についての新しい発見があることです。私にとって、ヨーコの作品は、それらについて考え直し、問い直すための揺るぎない招待状のような存在とも言えます。
──今回は小山登美夫ギャラリーの六本木と天王洲の 2 つのスペースで開かれている個展のキュレーターを務めています。まず、展覧会をつくる上でどんなことを考えたのか教えてください。
ヨーコの作品には、「見えるもの」と「見えないもの」、「存在するもの」と「存在しないもの」が、空間の中を占有します。展覧会コンセプトの下敷きになったのは、それらが空間の中でどうあるか、またそのバランスについてです。
象徴的なのは、展覧会タイトルにもなっている《A Statue was here(ひとつの像がここにあった)》。その作品は、壁にその文字が記されており、彫刻や絵画、イメージは全くありません。ただ「かつてここにあったのかもしれない」、あるいは「もしかしたら今もここにあるかもしれない」と想像すること、それを認めることで、何かが開けてくる。そうしたヨーコの作品の重要なエッセンスをひとつ、キーワードにしました。
また、ヨーコの作品は、インストラクションの作品が有名ですが、絵画や彫刻など、日本ではあまり知られていないものもあります。中には70年代以降、ほとんど展示されてこなかった作品もあり、それらも今回、日本で紹介することも意図したことです。
美術というスケールを超え、た社会活動、平和活動へと展開──特に、六本木のスペースでは、彼女の「コンセプチュアル・オブジェクト」もひとつ見どころです。これは、置かれているものに対し、鑑賞者が頭あるいは心の中で何かを想像することで、成立する作品ですが、抽象的なオブジェととも、一部、タバコや塩入れなど、日用品も使われていることも印象的でした。
そうしたレディメイド(既製品)を作品に用いることも、ヨーコにとって重要なことだったのかもしれません。レディメイドというと、私たちはマルセル・デュシャンを思い浮かべます。デュシャンは既製品を、慣習的なアートの概念を覆すために作品に取り入れました。
ただ、ヨーコの場合、「芸術家の役割は破壊することではなく、ものごとの価値を変えることだ」とも言っていますが、こうしたありふれたものを使いつつ、鑑賞者に新たな思考、新たな世界の見方を促すことに目を向けました。
レディメイドそのものに目を向けさせるのではなく、それらを組み合わせて新しいもの、新しいアイデアを提示することがヨーコにとって重要だったということです。
また、こうしたヨーコの作品が促す眼差しの変化は、それぞれの生活のあらゆる側面に広がっていく可能性を持つものです。ヨーコにとっても、それは同じで、彼女は以降、社会の固定観念に対し、個人として何ができるのか、そして、それは美術というスケールを超えて、戦争をなくし、新しい社会を創造するために何ができるのかといった社会活動、平和活動へ展開されていくことになります。
「作品が白であっても、持っている人は好きな色に変えてもいい」──白や透明のものが多く見られます。こうした色は、オノさんにとって特別なものだったのでしょうか。
白あるいは透明で無色は、観客に思考を促し、自由に解釈してもらえる唯一の色なのかもしれません。白ではなく赤いキャンバスを提示すると、もしかしたら既に完成されれたもののような感じがしますよね。ヨーコは、「自分の作品が白であっても、持っている人は好きな色に変えてもいい」とも言っていましたが、未完成であることも彼女にとって重要なことです。
──例えば、ミニマリズムとは違うものだということでしょうか?
確かに、形式的な点で見れば、ミニマリズムの作品として解釈することもできるかもしれません。ただ、そういった形式主義的なミニマルアートは、作品に付随する感情や詩情を排除する傾向にある一方で、むしろ、ヨーコの作品は、感情や詩情を内包し、それを人と作品の関わり方や出会い方を開く方法として使われているように思います。
──また、六本木では、壊れた陶器を来場者が自由に組み立て、オブジェにするような作品もあります。
2011年に起こった東日本大震災の際にも、ヨーコは復興を願う作品制作や活動を行いましたが、今回の作品では、2024年の能登半島地震で、壊れてしまった陶器を用いています。会場では、来場者がこうした陶器をヒモやテープで固定し、オブジェのようなものをつくっていますが、興味深いのは、ヨーコは「知恵を持って直しなさい、愛を持って直しなさい それは地球を直すことにもなるでしょう」とメッセージを残しているものの、具体的なアプローチについては示していないことです。
壊れたもの、失われたものとして、目の前にある陶器の破片に対し、来場者は元通りになるように繕うこともできるし、まったく新しいかたちにすることもできる。それぞれ自分自身がアイデアを持ち込めるようにしています。それは、ヨーコにとって、人々が自分自身で新しく未来を築くことと同義なのです。
こうした作品のバックグラウンドには、ヨーコが第二次世界大戦の経験者であること、また、これらが、日本の金継ぎ、あるいは願い木や折り鶴などの日本の伝統を連想させるものでもあることも重要なことでしょう。
──天王洲のスペースでは、鑑賞者が直接作品に関与するような参加型のものが見られます。例えば、来場者がボールに白い布を巻きつけていく《Wrapping Piece》。それは、1人の来場者ではなく、ここを訪れたたくさんの人が関わることで、ボールが大きくなり、作品がより魅力的になっていく。参加型といっても、1人の来場者ではなく、なるべく多くの人の関与することが重要になっていることも興味深い点です。
その点について、端的にヨーコの考えを示しているのが、「この世界、この人生において、人々が集まり、共に動かなければ、何も生まれない」という彼女の言葉だと思います。
なお、この布でラッピングする作品について説明すれば、それは1962年に日本で初めて制作され、以降、さまざまなかたちで展開されてきました。自分を巻いたり、他の人を巻いたり、特には演奏中のオーケストラの演奏者を包んだり、また彫刻を包んだりと。
今回、天王洲のスペースに展示している《Wrapping Piece》は、そのバージョンの一つで、以前にもこうしたボールと白い布を用いた作品は、1966年、ロンドンのインディカ・ギャラリーで初めて発表されました。そこでもヨーコは、来場者にボールに白い包帯を巻いていくように呼びかけました。そうしてどんどん大きくなっていく白いボールは、この作品のもとに人々が集まり、共に動き、結束した証でもありました。少し笑い話のようにも聞こえますが、それは、その時、人々が信じられないほど結束した証です。
また、ヨーコの作品では、こうした物理的な参加だけでなく、六本木のスペースの作品にあるような、精神的な参加、心による参加を促すものもあります。ヨーコが、さまざまな作品で、その両方の参加を促してきたのも重要なことかもしれません。芸術においても人生においても、何か変化を現実に起こすためには、その両方が必要なのです。
オノ・ヨーコ「A statue was here 一つの像がここにあった」会期:~7月5日(土)
※小山登美夫ギャラリー六本木・天王洲の2つのスペースで同時開催
小山登美夫ギャラリー六本木
住所:東京都港区六本木6-5-24 complex665 2F
開廊時間:11:00~19:00
休廊日:日・月曜、祝日
小山登美夫ギャラリー天王洲
住所:東京都品川区東品川1-33-10 Terrada Art Complex I 4F
開廊時間:11:00~18:00
休廊日:日・月曜、祝日
https://tomiokoyamagallery.com/
文・松本雅延 編集・橋田真木(GQ)
こんな記事も読まれています
査定を依頼する
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
おすすめのニュース
-
-
-
ベストカーWeb0
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
-
-
motorsport.com 日本版0
愛車管理はマイカーページで!
登録してお得なクーポンを獲得しよう
おすすめのニュース
-
-
-
AUTOCAR JAPAN0
-
ベストカーWeb0
-
WEB CARTOP25
-
日刊自動車新聞2
-
-
AutoBild Japan0
-
AUTOCAR JAPAN0
-
-
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
WEB CARTOP26
-
motorsport.com 日本版0
-
-
-
AUTOSPORT web0
-
-
-
-
レスポンス3
-
-
ベストカーWeb0
-
Auto Messe Web0
-
-
-
-
業界ニュースアクセスランキング
-
コンビニではなぜ「前向き駐車」推奨する!? 実は「意外な理由」があった? 無視したら「罰則」は? いったい何が問題なのか
-
「木村拓哉」が“愛車”の「高級バイク」を公開し話題に! 「何しても様になる」声も!カッコ良すぎる「木村拓哉モデル」とは
-
日本の「対艦番長」F-2導入検討――フィリピン本気? 能力的にはバッチリだけど“現実的とは全く思えない”ワケ
-
新時代の自衛艦に搭載する「新ジャンル砲」ついに出荷! 防衛省が画像を公開 搭載された姿まもなく披露か
-
海自の「最新ステルス艦」が偉業達成! “海中に潜む刺客”を画期的な方法で爆破する瞬間を捉えた画像が公開
あなたにおすすめのサービス
あなたの愛車、今いくら?
申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!
新車見積りサービス
店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!






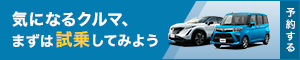
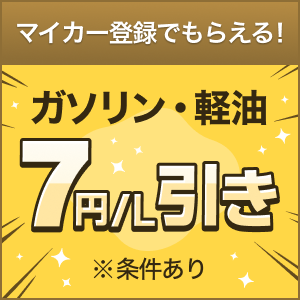
みんなのコメント
この記事にはまだコメントがありません。
この記事に対するあなたの意見や感想を投稿しませんか?